 AIワークフロー
AIワークフロー AIワークフローで解き放たれるビジネスの未来:仕事の効率と未来志向をデザインする
私たちは今、テクノロジーの進化がかつてないスピードで進む時代を生きています。その中でも特に注目を集めているのがAI(人工知能)です。AIは単なる流行語ではなく、私たちの働き方、ビジネスのあり方を根底から変革する可能性を秘めた強力なツールです...
 AIワークフロー
AIワークフロー  マーケティング
マーケティング 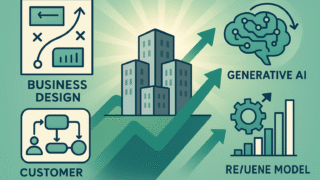 中小企業
中小企業  BUSINESS DESIGN
BUSINESS DESIGN  BUSINESS DESIGN
BUSINESS DESIGN 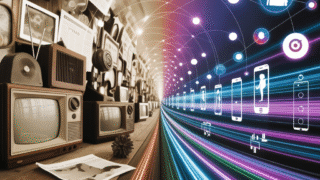 BUSINESS DESIGN
BUSINESS DESIGN