はじめに:なぜ、地方の逸品は「売れない」のか?
日本各地には、世界に誇るべき素晴らしい産品や技術、サービスが数多く眠っています。 しかし、その多くが担い手不足や市場の縮小という大きな壁にぶつかり、その輝きを失いかけているのが現実です。 「良いものを作っている自信はある。でも、どうやって売ればいいのかわからない」「後継者がいない」——。そんな悲痛な叫びが、全国の地方企業から聞こえてきます。
この根深い課題に対し、私たちは新たな処方箋を提言します。それが、「人的サプライチェーン」の構築です。
これは、従来の「地方で人材を確保する」という単純な発想から一歩踏み込み、「地方の産業主体(=生産拠点)と、中央(=大消費地・市場)の販売拠点を、共通の想いを持つ『人材』で繋ぎ、生産から販売までの一気通貫の流れを強固にする」という全く新しい戦略です。
具体的には、
- 地方の生産現場では、地域に根差した「地方人材」がその技術と文化を継承し、ものづくりの核を担う。
- 中央の販売・マーケティング拠点では、同じく「地方人材(地元出身者や地方に想いを持つ人材)」が、その土地の製品への深い理解と情熱を武器に、市場を開拓する。
この両輪を回すことで初めて、地方の産品に込められたストーリーや価値が消費者に正しく伝わり、持続的なビジネスが生まれるのです。本記事では、この「人的サプライチェーン」を構築し、地方産業を再生させるための具体的な方法論を、約10000字のボリュームでステップ別に徹底解説します。これは単なる採用論ではありません。企業の未来、そして地域の未来を左右する、新しい経営戦略の教科書です。
第1章:分断された「つくる」と「うる」〜地方産業の構造的欠陥〜
なぜ今、私たちは「人的サプライチェーン」という概念を提唱するのでしょうか。その背景には、多くの地方産業が抱える、深刻かつ構造的な問題が存在します。
1-1. 地方が抱える「生産」の課題
地方における課題は、単なる人手不足に留まりません。
- 技術・ノウハウの断絶: 長年培われてきた職人技や独自の製造ノウハウが、後継者不足によって失われつつあります。これは、企業の競争力の源泉そのものを失うことに他なりません。
- 担い手の高齢化: 若い世代が地域を離れることで、現場の平均年齢は上昇の一途をたどっています。これにより、新たな技術の導入や、体力的に厳しい作業への対応が困難になっています。
- 内向きな視点: 長年、地域内の顧客や既存の取引先との関係性で事業が成り立ってきたため、外部の市場や消費者のニーズの変化に対応しきれていないケースが散見されます。
これらの課題は、地方における「ものづくり」の土台を静かに蝕んでいます。
1-2. 中央との「販売」における断絶
一方で、いくら素晴らしい製品を生み出しても、それが消費者の手に届かなければ意味がありません。ここに、地方と中央(市場)との大きな断絶が存在します。
- 「良いものであれば売れる」という幻想: 製品の品質には絶対の自信があるものの、その価値を伝えるマーケティングやブランディングのノウハウが決定的に不足しています。
- 販路開拓の壁: 中央のバイヤーや消費者との接点がなく、どのようにアプローチすれば良いのか分からない。都市部の流通構造を理解している人材もいません。
- コミュニケーションの齟齬: たとえ商談の機会を得たとしても、生産者の「想い」と、市場が求める「価値」との間にズレが生じ、ビジネスチャンスを逃してしまうことが少なくありません。
この「生産」と「販売」の深刻な分断こそが、地方産業のポテンシャルを最大限に引き出せていない最大の原因なのです。
1-3. 新概念「人的サプライチェーン」〜分断を繋ぐ架け橋〜
「人的サプライチェーン」は、この分断された流れを「人」の力で繋ぎ直す試みです。
【新しい人的サプライチェーンの全体像】
- 源流(地方・生産拠点):
- 役割: 高品質な製品・サービスの開発と生産。技術の継承と革新。
- 人材: 地域に根差し、ものづくりに情熱を注ぐ「地方人材(生産の担い手)」。
- 下流(中央・販売拠点):
- 役割: 市場調査、マーケティング、ブランディング、販路開拓、顧客との関係構築。
- 人材: 地元の製品に深い理解と愛着を持ち、中央の市場を熟知した「地方人材(販売の担い手)」。
- 流れ(連携):
- 中央の販売担当者が掴んだ市場のニーズや顧客の声を、地方の生産拠点に的確にフィードバックする。
- 地方の生産者が込めた製品への想いやストーリーを、中央の販売担当者が熱量を持って顧客に伝える。
この情報の双方向コミュニケーションと想いの共有を、「同じ故郷を持つ」「同じ地域を愛する」という共通項を持つ人材が担うことで、強固な信頼関係が生まれ、サプライチェーン全体の価値が最大化されるのです。
第2章:【ステップ1】現状分析と戦略策定 ~自社の「流れ」を設計する~
壮大な構想も、まずは足元を見つめることから始まります。「人的サプライチェーン」の構築において、最初のステップは自社と自社を取り巻く環境を徹底的に分析し、どこに人材を配置すべきかという明確な戦略を描くことです。
2-1. サプライチェーンのボトルネックを特定する
まず、自社の事業を「原材料調達 → 生産・加工 → 商品化 → マーケティング → 販売 → アフターサービス」といった一連のサプライチェーン(価値連鎖)として捉え、それぞれの段階における強みと弱みを洗い出します。
- 生産プロセス: 技術力は高いか? 生産効率は良いか? 品質は安定しているか? → ここに課題があれば、地方拠点での技術継承者や生産管理者が必要。
- マーケティング・販売プロセス: 自社製品の強みを言語化できているか? ターゲット顧客に情報が届いているか? 新規の販路はあるか? → ここに課題があれば、中央拠点でのマーケティング担当者や営業担当者が必要。
- 企画・開発プロセス: 市場のニーズを商品開発に活かせているか? 競合との差別化は図れているか? → ここに課題があれば、地方と中央を繋ぐ商品企画担当者が必要。
この分析を通じて、「我が社は『つくる力』は強いが『うる力』が弱い」あるいは「基本的な生産力に課題がある」といった、人材配置における優先順位が明確になります。
2-2. 求める人材像の解像度を極限まで高める
ボトルネックが特定できたら、次にその課題を解決できる人材像を具体的に定義します。重要なのは、「地方拠点」と「中央拠点」、それぞれの役割を明確に分けることです。
【求める人材像の定義(例:地方の食品メーカー)】
| 地方拠点人材(生産・開発) | 中央拠点人材(販売・マーケティング) | |
| ミッション | ・伝統製法を守りつつ、新商品の開発をリードする ・若手従業員への技術指導と生産管理体制の強化 | ・首都圏の高級スーパーや百貨店への新規販路を開拓する ・WebサイトやSNSを活用したデジタルマーケティング戦略を立案・実行する |
| 必須スキル | ・食品製造に関する専門知識、品質管理の経験 ・チームマネジメント経験 ・地域とのリレーションシップ構築能力 | ・食品業界での営業またはマーケティング経験 ・ECサイト運営やWeb広告運用のスキル ・プレゼンテーション能力、交渉力 |
| マインド | ・ものづくりへの探求心と情熱 ・地域文化への敬意と貢献意欲 ・長期的な視点で事業を育てる粘り強さ | ・故郷の産品を世に広めたいという強い想い ・市場の変化に柔軟に対応するスピード感 ・チャレンジ精神と成果へのこだわり |
| ペルソナ | ・地元の農学部を卒業し、食品会社で5年間の製造経験を積んだ30歳 ・地元にUターンし、地域に貢献したいと考えている | ・A県出身で、東京の大学を卒業後、広告代理店で3年間勤務した25歳 ・自身のスキルを故郷のために活かしたいと考えている |
ここまで具体的に人材像を描くことで、採用活動におけるメッセージがシャープになり、候補者とのミスマッチを劇的に減らすことができます。「誰でも良い」ではなく、「あなたの、その経験と想いこそが必要だ」と伝えることが、優秀な人材の心を動かすのです。
第3章:【ステップ2】地方拠点(生産)の強化 ~技術と文化の砦を築く~
人的サプライチェーンの源流であり、すべての価値の源泉となるのが地方の生産拠点です。ここの土台が揺らいでいては、下流(販売)でいくら頑張っても意味がありません。地域に根差した人材を確保し、育て、技術と文化の砦を強固にすることが急務です。
3-1. 人が集まる「引力」のある職場環境
これは前回の記事でも触れましたが、給与や休日といった条件面だけでなく、社員が「この会社で働き続けたい」と思える魅力的な職場環境が不可欠です。
- 働きがいと成長実感の提供: 明確なキャリアパス、権限移譲と挑戦の機会。
- 公正な評価と納得感のある報酬: 成果とプロセスの両方を評価する制度。
- ワークライフバランスの推進: 柔軟な働き方の支援。
特に地方拠点においては、「地域文化の継承者」としての誇りを醸成することが重要です。自社の仕事が、地域の伝統を守り、未来へと繋ぐ尊いものであるという意識を社員全員で共有することが、仕事へのエンゲージメントを高めます。
3-2. 待ちの姿勢から脱却!攻めの地元採用戦略
「求人を出しても応募が来ない」と嘆く前に、採用活動そのものを見直しましょう。
- 地域の教育機関との強固な連携: 地元の高校や大学に足を運び、自社の仕事の魅力を直接伝える。専門高校などと連携し、地域の産業を担う人材を育成するプログラムを共同開発する。
- 地域コミュニティへの積極的な関与: 地域のお祭りやイベントに参加し、地域住民との接点を増やすことで、企業の認知度と評判を高める。
- Uターン希望者への戦略的アプローチ: 自治体が主催するUターン者向けのイベントに参加し、都市部にいる地元出身者に直接アプローチする。
3-3. 育てて活かす!体系的な人材育成プログラム
採用はゴールではなく、スタートです。特に技術の継承が重要な地方拠点においては、計画的な育成が企業の生命線を握ります。
- OJT(On-the-Job Training)の仕組み化: ベテラン社員の持つ「暗黙知」を「形式知」へと転換する努力(マニュアル化、動画撮影など)を行い、メンター制度を通じて計画的に技術を伝承します。
- Off-JT(Off-the-Job Training)の充実: 外部研修への参加支援や、資格取得支援制度を導入し、社員の自己啓発を促します。
- 次世代リーダーの計画的育成: 将来の工場長や開発責任者となる人材を早期に選抜し、計画的なサクセッションプラン(後継者育成計画)を策定します。
強固な生産拠点があって初めて、中央で戦う販売部隊は自信を持って自社の製品を売り込むことができるのです。
第4章:【ステップ3】中央拠点(販売)の開拓 ~故郷の想いを市場の力へ~
ここからが、本戦略の真骨頂です。地方で生み出された価値を、いかにして中央の市場で最大化させるか。その鍵を握るのが、中央拠点に配置する「地方人材」です。
4-1. なぜ「中央」に「地方人材」を置くのか?
都市部には、営業やマーケティングのプロフェッショナルは数多く存在します。しかし、私たちはあえて「地方出身者」や「地方に想いを持つ人材」を中央拠点に採用することにこだわります。その理由は、彼らが持つ圧倒的な「当事者意識」と「翻訳能力」にあります。
- 熱量を伝えるストーリーテラー: 彼らは製品のスペックを語るだけではありません。その製品が生まれた土地の風景、生産者の顔、地域の文化といった背景にあるストーリーを、自身の原体験として熱量を持って語ることができます。この「物語」こそが、モノが溢れる現代において消費者の心を動かす最大の武器となります。
- 円滑なコミュニケーションブリッジ: 地方の生産拠点とのコミュニケーションにおいて、「阿吽の呼吸」が期待できます。方言や地域の慣習を理解しているため、微妙なニュアンスを汲み取り、円滑な連携を促進します。これは、外部の販売会社に委託するのとは決定的に違う点です。
- 的確な市場のフィードバック: 中央の市場で得た顧客の生の声やトレンドを、単なるデータとしてではなく、「地元のあの製品なら、こうすればもっと売れるはずだ」という当事者としての改善提案として地方にフィードバックすることができます。
彼らは単なる「販売員」ではなく、地方と中央を繋ぐ「大使(アンバサダー)」なのです。
4-2. 「故郷への貢献」をフックに口説き落とす採用術
では、どうすれば都市部にいる優秀な地方人材を見つけ出し、採用することができるのでしょうか。
- 採用メッセージの転換: 「営業職募集」といったありふれた求人ではなく、「あなたの故郷の逸品を、その手で全国区にしませんか?」「東京で培ったそのスキル、故郷のために使いませんか?」といった、貢献意欲に訴えかけるメッセージを発信します。
- 出会いの場の創出:
- Uターン・Iターンフェアへの積極出展: 自治体が主催するイベントは、まさにターゲット人材の宝庫です。
- 県人会や同窓会ネットワークの活用: 経営者自らが顔を出し、ビジョンを語ることで、リファラル(紹介)採用に繋がる可能性があります。
- SNSでの戦略的発信: LinkedInやFacebookで、地元出身のキーパーソンを探し、ダイレクトにメッセージを送る。会社の公式アカウントでは、中央で働く社員の活躍ぶり(仕事のやりがい、故郷への貢献実感など)を発信する。
- 「暮らし」ではなく「志」で惹きつける: 地方への移住を伴わないため、「自然豊かな環境」といったアピールは響きません。彼らの心を動かすのは、「自分のルーツである故郷に、自分の力で貢献できる」というキャリアの魅力と、事業の将来性です。
4-3. 「大使」を育てる育成とサポート体制
中央拠点で採用した人材が孤立せず、最大限のパフォーマンスを発揮できるような仕組み作りが不可欠です。
- 定期的な「里帰り研修」の制度化: 年に数回、地方の生産拠点に滞在し、生産工程を体験したり、生産者と直接対話したりする機会を設けます。これにより、製品への理解が深まり、現場との一体感が醸成されます。
- 地方と中央の情報共有インフラの整備: Web会議システムやビジネスチャットツールを導入し、日常的に顔を合わせたコミュニケーションが取れる環境を整えます。生産状況、在庫状況、顧客からのフィードバックなどをリアルタイムで共有します。
- 成果を正当に評価する人事制度: 中央拠点での売上や新規販路開拓といった成果が、地方拠点の社員を含めた会社全体の評価や賞与に反映される仕組みを構築します。これにより、「自分たちの頑張りが、故郷の仲間たちの喜びに繋がっている」という実感を生み出します。
第5章:【ステップ4】「人的サプライチェーン」の定着と循環 ~地域と共に育つエコシステムへ~
地方と中央、二つの拠点が「人」によって有機的に結ばれたら、その流れをより強く、太くしていくフェーズに入ります。目指すのは、一企業内にとどまらない、地域全体を巻き込んだエコシステムの構築です。
5-1. 物理的な距離を越える組織文化の醸成
地方と中央、物理的に離れた拠点が一体感を持って機能するためには、それを支える強固な組織文化が必要です。
- 共通のビジョンと価値観の浸透: 「私たちの力で、この地域の未来を創る」といった、全社員が共感できるミッション、ビジョン、バリューを策定し、あらゆる場面で繰り返し発信します。
- 相互リスペクトの徹底: 生産現場の社員は、市場の最前線で戦う販売担当者をリスペクトし、そのフィードバックに真摯に耳を傾ける。販売担当者は、ものづくりの担い手である生産現場の社員に常に感謝の念を持つ。この相互リスペクトが信頼関係の土台となります。
- 全社一体イベントの開催: 年に一度は全社員が一同に会するキックオフミーティングや社員旅行などを実施し、組織としての一体感を高めます。
5-2. 「個」から「群」へ!地域連携によるエコシステムの構築
自社の人的サプライチェーンが成功モデルとなれば、そのノウハウを地域全体に広げ、より大きなうねりを起こすことができます。
- 地域企業との共同採用・共同育成: 地域の複数の企業が連携し、中央で合同の採用説明会を開催したり、若手社員向けの研修を共同で実施したりします。これにより、一社ではアプローチできなかった層にもリーチでき、採用・育成コストの削減にも繋がります。
- 「地域商社」機能の共同設立: 地域の企業群が出資しあい、中央に共同の販売・マーケティング拠点(地域商社)を設立することも有効な戦略です。これにより、各社が単独で営業担当者を置くよりも、はるかに強力な販売網を構築できます。
- キャリアパスの地域内循環: 将来的には、「A社の生産管理職から、B社の中央営業職へ」といった、地域内の企業間での人材の流動化を促します。これにより、個人は地域に留まりながら多様なキャリアを築くことができ、地域全体としての人材リソースが強化されます。
5-3. PDCAによる継続的な最適化
この仕組みは、一度作ったら終わりではありません。市場環境や事業ステージの変化に合わせ、常に改善を続けていく必要があります。
- P(Plan): 地方拠点、中央拠点それぞれに具体的なKPI(採用人数、定着率、新規販路開拓数、売上目標など)を設定する。
- D(Do): 計画に沿って実行する。
- C(Check): KPIの達成度を定期的に測定・評価し、両拠点の社員にヒアリングを行い、連携における課題を洗い出す。
- A(Act): 評価結果に基づき、採用戦略、育成プログラム、コミュニケーション方法などを見直し、改善する。
この地道な改善のサイクルこそが、企業の成長と地域の発展を支える、強くしなやかな人的サプライチェーンを築き上げるのです。
まとめ:分断を乗り越えた先に、地方創生の真の姿がある
本記事で提唱した「人的サプライチェーン」は、単なる採用手法のハックではありません。それは、地方産業が抱える「生産と販売の分断」という構造的欠陥を、「人材」という最も重要な経営資源によって繋ぎ直し、企業の競争力を根本から再構築する経営戦略です。
地方で、誇りを持ってものをつくる人がいる。
中央で、故郷の想いを背負ってものをうる人がいる。
この二つの情熱が、共通のビジョンに向かって一つになった時、そこにはこれまで誰も見ることができなかった、力強く、新しい地方創生の未来が拓かれるはずです。
道のりは簡単ではないかもしれません。しかし、この戦略は、あなたの会社が、あなたの地域が、未来に向かって生き残るための、最も確実な道筋を示していると私たちは確信しています。さあ、あなたの会社から、生産と販売の壁を打ち破る、新しい物語を始めようではありませんか。
この”守破離流採用デザイン”についてご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。



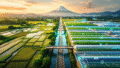
コメント